自然の造形からヒントを得るのは、デザイナーの常套手段だ。多くのデザイナーが、自然のつくりだすカタチの「意味」を切り取って、自らのデザインに生かしている。 しかしこのやり方はもはや、デザイナーの独壇場ではなくなってきているようだ。
 上:木漏れ日からヒントを得たと思われる、ルイス・ポールセンのCollage Pendant(デザイナー:Louise Campbell)、下:氷の塊を彷彿とさせる、ティナント・スプリングウォーター(デザイナー:Ross Lovegrove)
上:木漏れ日からヒントを得たと思われる、ルイス・ポールセンのCollage Pendant(デザイナー:Louise Campbell)、下:氷の塊を彷彿とさせる、ティナント・スプリングウォーター(デザイナー:Ross Lovegrove)
ベルギー・ブリュッセル大学のMarco Dorigo教授らのグループは、アリがフェロモンを介して情報伝達することで、集団として非常に高度で知的な振る舞いをすることに目をつけ、これをACO(Ant Colony Optimization)と呼ばれる工学的なモデルで表現している。ACOは電話交換網や、パケット交換のアルゴリズム、移動型ロボットの制御など、様々な分野で応用されている。 このような工学的手法をNature Inspired Algorithm(自然界からインスパイアされたアルゴリズム)と呼ぶ。
自然界の生物は、一匹一匹は単純な判断機構しか持たなくとも、群全体として目的性を持った振る舞いをする現象を発現することが多い。これを、群知能(swarm intelligence)という。鳥の集団飛行や、蜂の集団行動も群知能の代表例だ。
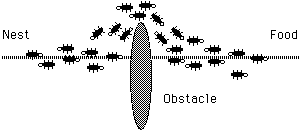 上:アリは障害物を避けながら巣からエサ場へ向かう。エサを見つけたアリは誘引フェロモンをバラ撒きながら巣へと戻る。下:より短い経路を辿って巣と餌場を往復すれば、そのエリアのフェロモンの濃度が濃くなる。このように、フェロモンというメディアを介してアリ同士がコミュニケーションすることで、結果的に巣からエサ場への最短経路が形成される。
上:アリは障害物を避けながら巣からエサ場へ向かう。エサを見つけたアリは誘引フェロモンをバラ撒きながら巣へと戻る。下:より短い経路を辿って巣と餌場を往復すれば、そのエリアのフェロモンの濃度が濃くなる。このように、フェロモンというメディアを介してアリ同士がコミュニケーションすることで、結果的に巣からエサ場への最短経路が形成される。
サイエンスライターのJanine Benyus氏は、バイオミミクリーと呼ばれる活動を通じて、自然界からインスパイアーを得たモデルをもとに、サステナブルな概念をわかりやすく説明してくれている。
自然は、意匠権も著作権も特許権も主張せず、いつの時代もデザイナーやエンジニアに無限の発想をもたらしてくれる。なんと寛容な情報源なんだろうか。
2008年5月1日木曜日
自然から学ぶデザイン
ラベル:
エスノグラフィ,
コミュニケーションデザイン,
情報デザイン,
発想法



